論文紹介:トイレトレーニングについて①
こんにちは、e-URO2023です!
更新がだいぶ遅れてしまいました^^;
4月は環境がガラリと変わるので、忙しくなりますね。
言い訳はさておき、本日はトイレトレーニングについての論文を読みましたので、その紹介です。
できるだけわかりやすく説明できるように頑張りますね。
では始めます!
トイレトレーニングのReview article
2021年に出された、新しい論文を読みました。
Toilet training methods in children with normal neuropsychomotor development: A systematic review
2021年にJournal of Pediatric Urologyに掲載されたReview articleです(1)。
この論文では、様々なトイレトレーニングの方法を検証しています。
今回は論文の前半部分、トイレトレーニングの歴史と、様々なトイレトレーニング法について解説します。
トイレトレーニングの歴史
①19世紀後半から20世紀前半
トイレトレーニングは親任せで各々の方針に任されていたようです。コレと言ったやり方はなかったようですね。
②1932年〜
アメリカ政府が”Child Care”と呼ばれた本を出版しました。
この本では、トイレトレーニングを生後8ヶ月まで完了することが推奨されていました。
現代からすると、めちゃくちゃ早いですよね。
更に、排泄を促すために"soap stick"なるものを使って直腸を刺激する「強制的排便トレーニング」を行っていたようです。
絶対に真似しないでください!!
③1940年代
小児専門家たちが、厳格なルールに基づくトイレトレーニングに反対するようになりました。
というのも、早期に厳格なトレーニングを行うことはむしろ子供の禁制獲得の失敗、更には行動異常を引き起こす可能性が指摘されたからです。
また同じ頃より、トイレトレーニングは子供が興味を持ち始めたら開始するように、親に意識付けされるようになってきました。
④1960年以降
1962年、Brazeltonらによって、"Child-oriented approach"が提唱されます。
1973年、AzrinとFoxらによって、”Structured behavioral approach”が提唱されました。
どちらも、こどもの目線を大事にした、子供中心のトイレトレーニングです。
以後、様々なトイレトレーニング法が開発されてきましたが、基本的には上記の"Child-oriented approach"と”Structured behavioral approach”の2つのグループに大別されます。
つぎに、これらトイレトレーニング法について簡潔に説明していきますね。
英語の論文の紹介なので、英語が多めなのはご容赦ください^^;
Child-oriented approach
①Brazelton child-oriented method
こどもが「やる気」になった時にトイレトレーニングを開始する、というアプローチ方法です。トイレトレーニングに至るまでに、3本の柱があるとBrazeltonは述べています。
1. 生理的な成熟(座ったり、歩いたり、着替えることができたり、2時間はオムツにおしっこをしていない、など)
2. 外的刺激への理解(指示を理解して行動できること)
3. 自尊心と動機(真似しようとする、親に共感しようとする、自己決定する、独立心をもつ、など)
Brazeltonの手法では、「おまる」が重要アイテムです。
・トイレに興味をもちはじめたら、おまるを準備。
・おまるは「こどものもの」。こどもが手に取りやすい場所に置くことが大事。まずは”おまる”に興味を持たせること。
・"おまる"に興味をもったら、"おまる"を使う意味について教える(ウンチのついたオムツを見せて、ウンチをきれいに流す場所だよと教える、など)。
・"おまる"に座らせることを強制しない。
・"おまる"に座ってみようとしたら、ドアを締めて恥ずかしい思いをさせないように気を配ること。
・できないことを叱ったり罰を与えるのではなく、できたら褒める。ご褒美を上げてもいい。
このように、あくまでも子供が主体的にトイレトレーニングを行っていくという方法です。
1962年に開発された古い手法ですが、現代でも応用可能なトレーニング方法だと思います!
②American academy of pediatrics guidelines: child-oriented approach
Americal academy of pediatrics (AAP)が作成しているガイドラインでは、ほぼBrazeltonの手法が推奨されています。
しかし、「ご褒美をあげること」は推奨していません。
また、2-3歳でトイレトレーニングを開始することを推奨しています。
Structured behavioral approach
①Azrin and Foxx method
1973年にAzrinとFoxxによって考案された手法です。
かなり綿密な過程が組み込まれています。
例えば、
・気が紛れるもののない、トレーニングスペースを確保する
・トレーニングに必要な物品を準備する(チャイルドシート(?)、着替え用の服、トイレトレーニングを教えるための人形、など)
・トイレトレーニングの前に十分に水分をとらせる
・おまるに行く⇒数分間座る⇒パンツを上げ下げする…
など各過程が細かく決められていて、それぞれの過程で子供ができたら褒めてあげることが大事である、とのことです。
Brazeltonらの方法のように、叱ったり褒め忘れなどをしないように注意されています。
ちょっと細かすぎるからか、最近はあまり行われていないようです^^;
②Intensive toilet training method
尿意や本人の意志は関係なく、時間を決めてトイレに誘導する方法です。
その都度、親は"おまる"もしくはトイレに行くべきかどうかを尋ねます。
オムツやパンツが濡れていなければ褒めますが、アクシデントがあれば叱る、などやや親本位で"しつけ"的なやり方ですね。
③Assisted infant toilet training
乳児期(1歳未満)に行うトイレトレーニングで(ちょっと早すぎる!!)、親が子供の排泄サインを自覚したら、抱っこなど子供が排泄しやすい体勢を取らせます。
子供に排泄を促すように音を発します(し〜〜っ、とか、ブリブリブリ〜、とかですかね?)。子供が排泄できたら褒めてあげます。
そもそも、子供を育てた立場としては、「子供の排泄サイン」なんて中々わからないですけどね…
④Elimination communication
なんと、生まれた時から行うトイレトレーニングです(!!)
まず前提として、親がボディーランゲージ・排尿/排便時の音を発する練習・乳児が排尿や排便をしようとするリズムの習得が必要になります(無理ゲー)
そして、オムツを使わずにシンクやトイレ、おまるなどに子供を座らせて排泄させる、とのこと。
メリットは、子供にとってより快適なのと、オムツを使わないので環境によいと(笑)
⑤Daytime wetting alarm diaper
オムツが濡れるとアラームが鳴るシステムを用います。
アラームが鳴ったら子供をトイレに誘導し、排尿させます。
1歳半から3歳頃に行うトイレトレーニングとのことです。
これは夜尿症の治療で使われるアラーム療法を、日中に行うようなものですね。
泌尿器科医にはしっくり来るトレーニング法ですが、ここまで必要かなと若干思ってしまいます。
まとめ
いかがでしたか?
いろいろなトイレトレーニングの方法がありましたね。
トイレトレーニングって、親としては教えられることもないですし、教科書もないし、皆さんネットや知り合いの口コミとかで試行錯誤しながらしているものと思います。
私自身も、子供のトイレトレーニングが全然進まず、不安な時期がありました。
でも今回論文を読み、色々な方法が試されてきた歴史があることを知ることができました。
先人たちの歩んできた道を学んで、活かしていきましょう!
次回は論文の後半、それぞれのトイレトレーニング法の検証になります。
参考文献
1) de Carvalho Mrad FC et al. Toilet training methods in children with normal neuropsychomotor development: A systematic review. J Pediatr Urol. 2021;17:635-643.
・いらすとや https://www.irasutoya.com/
・フリー画像・写真素材 写真AC https://www.photo-ac.com/
・イラストレーターわたなべふみ https://www.fumira.jp/
ご質問や、間違っているよなどの指摘がありましたら、何なりとコメント欄に書き込んでいただければ幸いです。適宜修正・追記していきます。
↓↓↓



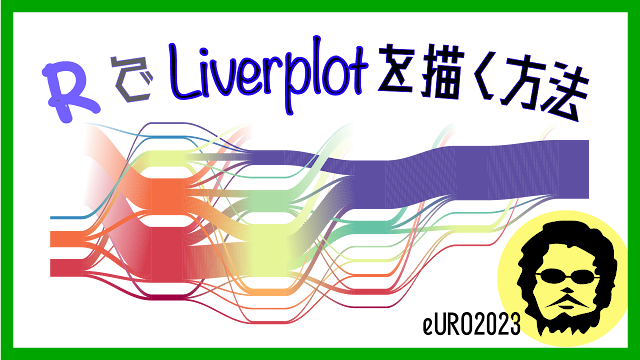

コメント
コメントを投稿